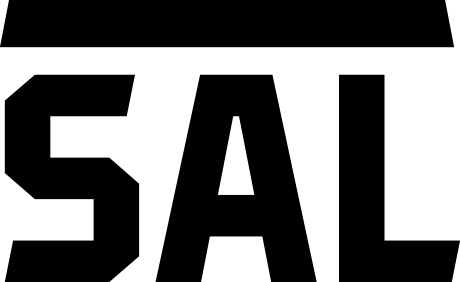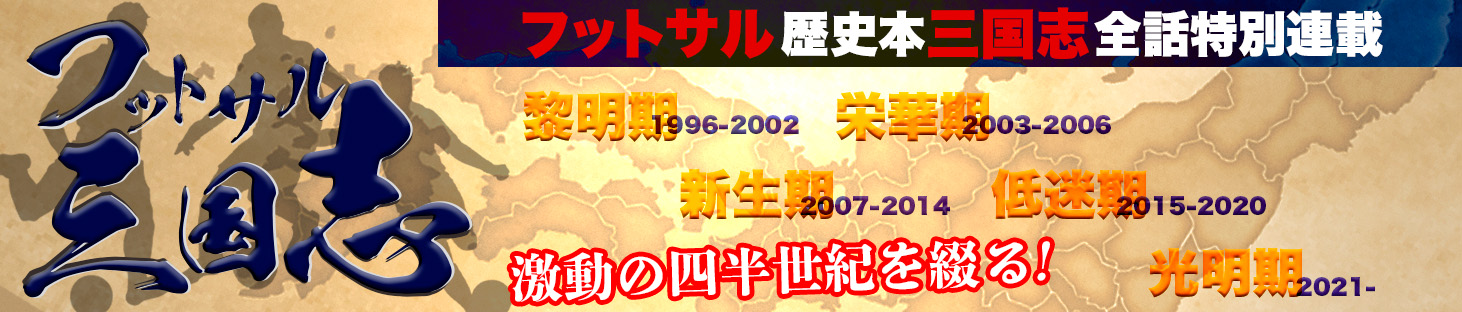更新日時:2025.11.04
【連載】その1 悲願達成に向けて/その2 新たなメディアの登場/その3 日本代表応援団の発足|第7章 ワールドカップ|第2部 栄華期|フットサル三国志

PHOTO BY
【連載】フットサル三国志|まとめページ 著者・木暮知彦
第2部 栄華期
第7章 ワールドカップ(2004年2月~2004年11月)
その1 悲願達成に向けて
その2 新たなメディアの登場
その3 日本代表応援団の発足
その1 悲願達成に向けて
2004年2月、選手権が終わってわずか1週間後、早くも日本代表候補合宿が始まった。この年は「見るフットサル」の究極とも言うべき第5回ワールドカップ開催の年であった。〝バンコクの悲劇〟と言われ、4位に終わった第2回アジア選手権から4年が経ったのである。そして、4月に行われる第6回アジア選手権で3位以内を確保すればワールドカップに出場できるのだ。
ちなみにバンコクの悲劇からのアジア選手権の成績は、第3回(テヘランにて開催、木村和司監督)は4位、第4回(ジャカルタにて開催、原田理人監督)は2位、第5回(バンコクにて開催、原田監督)は2位となっている。むろん、優勝はいずれもイランである。しかし、この2位は意味が大きい。なぜなら、常勝のイランとは予選リーグでは同一ブロックにならず、決勝トーナメントも別の山の組み合わせになるからである。
招集された代表候補は、ゴールキーパーを含め、合計20名であった。そのうち14名が代表としてアジア選手権に参加する。地域の内訳を見ると、関東が12名、関西が6名と半数以上が関東で占められた。残りの2名は東海地域のゴールキーパー川原永光とFC琉球に所属していた関係で地域は九州・沖縄の比嘉リカルドである。
セルジオ・サッポ監督になって新しく呼ばれた選手は、関東では、小野大輔、稲葉洸太郎、稲田祐介、ゴールキーパー石渡良太であった。いずれも本書の中では登場してきている選手で、いつ候補に呼ばれてもおかしくない選手たちであった。中でも注目は、小野と稲田の2人だ。なぜなら、彼らの役割はピヴォだからである。すでに、ピヴォには相根澄、木暮賢一郎がいたが、相根はベテランで、木暮はピヴォに抜擢されてから間もない。そこで、どうしても強化が必要だったのである。
実際、小野、稲田は日本代表に選ばれ、稲田7得点、小野5得点と大活躍する。ちなみに、相根、木暮も選ばれており、1得点、9得点を挙げている。この4人で合計22得点、チーム全体が47得点であったから、半数近くを占めたことになる。サッポ監督がいかにピヴォを重用したかがわかる。
もう1人、注目の選手がいた。それは稲葉である。すでに、本書では「森のくまさん」というチームで民間大会のピヴォ!チャンピオンズカップに優勝、MVPを受賞したことで登場した。その副賞のブラジル留学に北原亘(のちに名古屋オーシャンス)と一緒に行ったが、その北原より先に日本代表に選ばれることとなった。なお、代表に選ばれた時の所属は「渋谷ユナイテッド」というチームで、東京都リーグ2位のチームであった。そこには、三国志を大きく変えたかも知れないドラマがあった。その話はのちに譲ることにする。
通年リーグの必要性が叫ばれ、チームの合従連衡を繰り返しながら、リーグの乱立を経てここまできた三国志の登場人物たちのみならず、日本フットサルの悲願達成なるか、運命の第6回アジア選手権は2004年4月16日からマカオにて開催される。
お宝写真は、来たるアジア選手権に向けて応援団が全国各地のフットサル施設、会場で集めた日の丸への寄せ書きにしよう。団長の山川太郎は、フットサルナビの取材でこう述べている。
「この旗を思いついたきっかけは、選手たちに日本中から応援されているということを伝えたかったからです。だから、全国から集めなくてはならなかったのです。熱い想いがビッシリと書かれた日の丸を見ていると何が何でもワールドカップの切符を勝ち取ると私たちも燃えてきました」

その2 新たなメディアの登場
運命の第6回アジア選手権およびワールドカップ出場の期待を前に、新たなメディアが動き出した。すでに紹介したとおり、これまで、雑誌は「ピヴォ!」、インターネットは「フットサルネット」と「FC JAPAN」が主なメディアであった。ネットでフットサルを扱っていた日刊スポーツとスポナビのフットサル版は存続していない。
ちなみに、メディアの興亡は、ピヴォ!、フットサルネット、FC JAPANに代表されるフットサル黎明の時代、この2004年前後の期待が膨らむ時代、そしてFリーグが始まった2007年前後から以降の時代の3つに分けることができる(その後、2020年代を取り巻く現在のメディアの詳報は本書では割愛する)。
ここでは、2004年前後の時代について紹介しよう。
まず、2004年1月にフットサル専門雑誌の第2誌目「フットサルナビ」がムック本として刊行される。発行元は白夜書房で、趣味・娯楽雑誌を主に発行していたが、フットサル好きの編集者・大久保洋介の企画が通って発行の運びとなったという。以来、先行したピヴォ!とは交互に隔月での発行が続いていた。4月には早速、第2号が発行され、アジア選手権を戦う日本代表の特集が組まれた。
そして3誌目、サッカーダイジェストでおなじみの日本スポーツ企画出版社が「フットサルダイジェスト」を発刊する。それは、日本代表のワールドカップ出場が決まったのちの2004年11月のことである。また、学研の「ストライカー」さらには「サッカーマガジン」も雑誌内でフットサルコーナーを設ける。
珍しいサイトもオープンする。それは、ラジオNIKKEIが提供する「フットサルラジオウェブ」である。インターネットでフットサルのニュースやインタビューなどの音声放送を流すサイトで、2003年から試験的に始まり、2004年2月から本格スタートした。キャスターは竹川英紀で、のちに女性パーソナリティとして景山のぞみ、小島くるみなどいわゆる〝芸能人女子フットサルタレント〟を起用するなどユニークな存在であった。
紙面をピンク色にしたユニークなサッカー専門新聞「エルゴラッソ」が発刊されたのは2004年10月である。夕刊のみの駅売りで、当時の発刊元は交通新聞社であった。金曜日にはフットサル紙面があり、日本代表、全日本選手権、地域リーグなどの情報を掲載していた。
また、スカイAのテレビ放送に加えて、7月からゴールネット株式会社、デジタルスタジオの協力により、インターネットによるビデオストリーミングサービスが始まった。今でこそ、Fリーグは有料の動画配信サービスを行っているが、2004年のこの頃から始まっていたことは画期的であった。
ポータルサイト系では、フットサルネットに加え、「フットサルタイムズ」が1年後の2005年4月にオープンする。のちにこの2つのサイトは、自ら執筆するばかりでなく、フリーランスのライターを起用するようになった。
このようにメディアの増加にともない、雑誌社専属、あるいはフリーランスのフットサル専門ライターや専門カメラマンが多数輩出することとなった。ここでは、少し前の先駆者を含め、彼らの状況を紹介しょう。
ライターの先駆者としては、学研の雑誌ストライカーでフットサル記事を担当する菊地芳樹がいる。菊地は大学時代にサッカーをしていたこともあって、神奈川県リーグでは選手活動もしていた。その経験を生かし、2001年にイランで行われた第3回アジア選手権には現地取材に行くなど先駆的活動を行っていた。雑誌ストライカーのサッカー記事、フットサル記事ばかりでなく、Fリーグ公式サイトの記事やフットサルポータルサイトのフットサルネット、フットサルタイムズに記事やコラムを書くなど活動は多岐に渡った。その後、菊地は、ストライカーの編集長となった。
2002年頃からフットサルネットにおいて先駆的なコラムを書いていたライター川村真也は、前述した2004年発刊のエルゴラッソのフットサル版の編集を手がけた。彼も先駆的存在と言える。
スペインで「ワールドオンライン」なるスペインを中心としたフットサルのニュース、技術情報をネット配信するサービスを行っていた座間健司がスペインに渡ったのも2004年である。この年の8月、スペインリーグのカステジョンが来日、親善試合を行うが、これをきっかけにスペインに渡るのであった。元々はフットサルマガジンピヴォ!の編集者であったが、2011年に雑誌ピヴォ!が休刊したことに伴い独立した。
同じく、河合拓も座間と同時期にピヴォ!のスタッフになったが、この頃、サッカーマガジンのスタッフに転身、時折フットサル記事を書いている。フットサルマガジンは、それまではフットサル記事を掲載する機会は少なかったものの、次第にその機会を増やしていった。
自らを「炎のフットサルライター」と呼び、熱い記事を書く田畑弦は、この頃、前述したフットサルラジオウェブ、フットサルナビを主なフィールドとして記事を執筆していた。
北健一郎がジャーナリスト専門学校を卒業、フットサル専門の記事を書くようになったのは、2005年のストライカーからであった。その後、フリーになり、フットサルナビ、フットサルネット、フットサルタイムズなどにも記事を書くようになった。サッカーや書籍の執筆にも活動範囲を広げ、「サカテク」「フットサル速攻マニュアル100」など、サッカー・フットサルで数多くの著書を世に送り出している。
その後、フットサル専門ポータルサイト「futsal EDGE」を立ち上げ、さらに、株式会社ウニベルサーレというスポーツメディア会社を設立、現在は「SAL」というフットサル専門サイトを運営するに至っている。
なお、この三国志はフットサルエッジに掲載されたものをリニューアルしたというわけである。
カメラマンでは、サッカー分野が主活動であるが、六川則夫が先駆者である。六川は、〝バンコクの悲劇〟が起こった2000年の第2回アジア選手権、テヘランで行われた2001年の第3回アジア選手権などを取材し、以降も節目の大会において現地での撮影を続けてきた。
もう一人、先駆的フリーのカメラマンとしては勝又寛晃がいる。勝又は、大学で写真を専攻、卒業後、2000年のスーパーリーグからフットサル取材を始め、プレデター(のちのバルドラール浦安)の専属カメラマンを務める他、2002年にジャカルタで行われた第4回アジア選手権を取材するなど、フットサル界に入っていった。フットサルマガジンピヴォ!、フットサルダイジェストなどでも活動してきた。
軍記ひろしは、フットサルグラフィックという法人を設立し、フットサル専門の写真サービスの代表を務めるなどユニークな活動を続ける人物だ。クライアントには、Fリーグをはじめ、いくつかのクラブでもオフィシャルカメラマンとして写真を撮ってきた。軍記のフットサルデビューは2004年頃であった。
時は2015年、フットサルの隆盛に期待を膨らませた時代から約10年が経過、念願の全国リーグであるFリーグもできた今日、メディアでどれだけ仕事ができるかというと正直、厳しい状況が続いている。いくつかのメディアは休止を余儀なくされ、ライター、カメラマンも転身あるいは兼業となっている。
さて、お宝写真であるが、「フットサルナビ」でワールドカップを特集した2004年11月号(第5号)にしよう。表紙は「キャプテン翼」でおなじみの高橋陽一が描くところの日本代表メンバーである。
ただし、フットサルナビは2017年12月15日号をもって廃刊となり、フットサル専門誌は日本では皆無となってしまった(2024年現在も、フットサル専門誌は存在していない)。
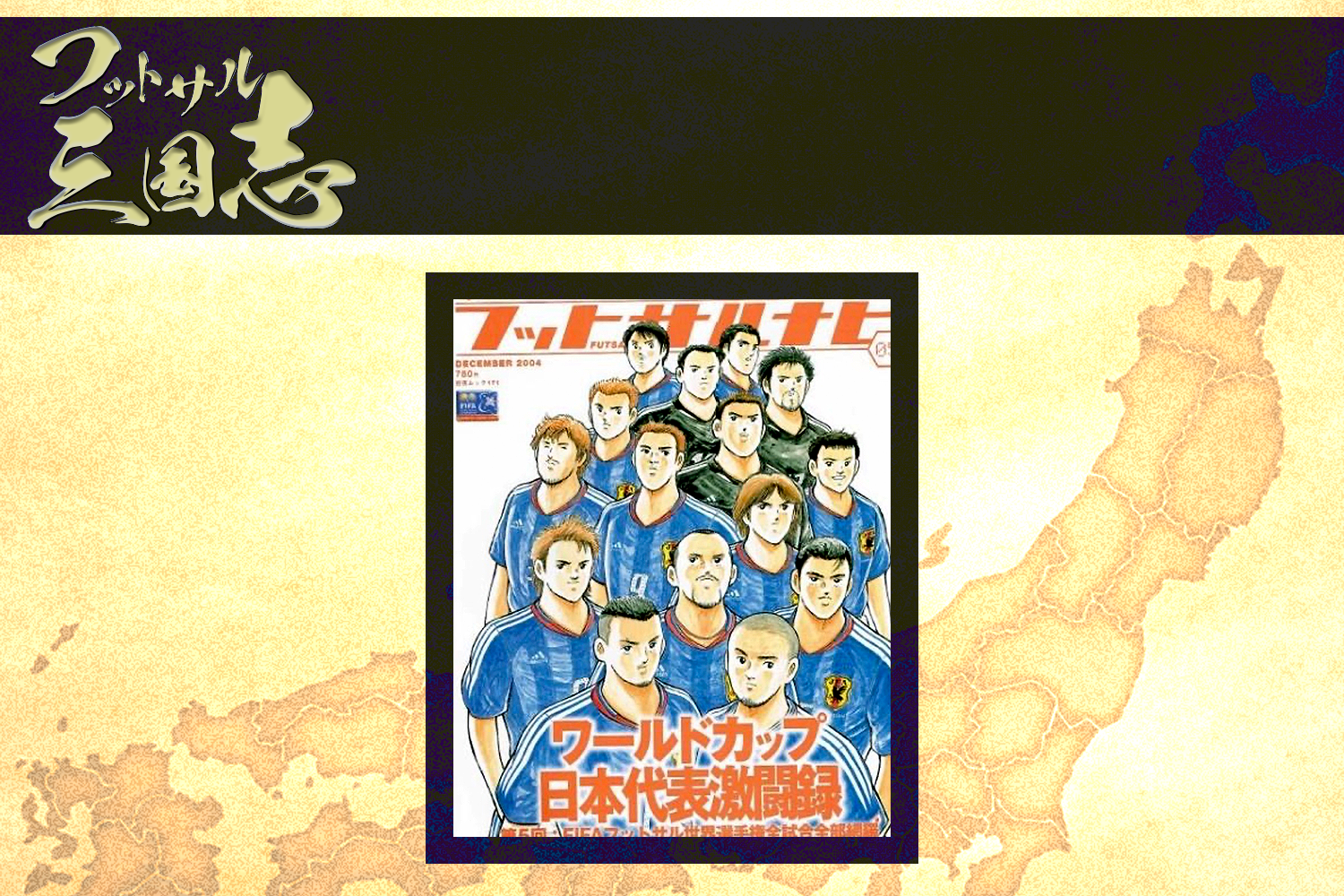
その3 日本代表応援団の発足
2004年3月、都内某所のブラジルレストランで、ある懇親会が開催された。日本代表応援団主催の第6回アジア選手権・日本代表壮行会である。会場には、日本サッカー協会フットサル委員長の栄隆男をはじめ、日本代表監督のサッポ、そして日本代表メンバー(定永久男、遠藤晃夫、市原誉昭、難波田治、木暮、小野、稲葉)が出席し、代表応援ツアー参加者、一般参加者から大きなエールが送られた。実質、日本代表応援団の発足である。
会場では、日本代表の試合ビデオが流され、サッポ監督の挨拶、選手の挨拶、応援団の挨拶などが行われ、ワールドカップ出場の決意のほどを大きく感じられる会合となった。おそらく、このような会合は、今ではなかなか開催にこぎつけられないだろう。当時は、なんとか世界に行ってもらいたい、世界に行けば何かが変わるはずだという関係者の想いがこれを実現させたものと思われる。
この集まりを契機に、応援団の名称は「Poeira」(ポエイラ)とした。名付け親はサッポ監督である。意味はポルトガル語で埃(ホコリ=「誇り」とのダブルミーニング)だそうで、「サポーターの応援がスタジアムに〝埃〟を巻き起こすくらい、情熱的で激しい」というコンセプトであった。むろん、有志でつくられた私的な応援団ではあるが、これを機会にフットサルを盛り上げようと、今まではスーパーリーグ、あるいは関東リーグでそれぞれのチームの応援をしていたシャークスのサポーターのトヨ、ガロのサポーターのワカンらのメンバーが集結したのであった。
団長を務めたのは山川太郎だ。山川は、高校時代はサッカー部に所属、その後、神奈川県リーグのフットサルチーム「湘南蹴族」でフットサルをプレーした。湘南蹴族は最後のシーズンのスーパーリーグにも参戦している。スーパーリーグは私的なリーグだったので応援も派手に行うことができ、選手、サポーターの交流も盛んに行われていた。したがって、十分な下地はできていた。本来なら2003年に日本で開催するアジア選手権で集結する予定であったが、SARSの影響で開催地を返上したことにより、今回のアジア選手権で集結となったという。
振り返ってみれば、アジア選手権がマカオ、ワールドカップが台湾(台北)と比較的日本の近くで、なおかつ治安の良い都市で開催されたことは幸運だったと言える。これが、ブラジルあるいはイランで開催となると集結も難しかったであろう。実際、ポエイラの影響でツアーも組まれ、多くの応援団がまずはマカオに集まることができた。
山川をはじめ、サポーターの多くは日本代表を応援したい気持ちは当然のことながら、こんなにおもしろいスポーツをもっとみんなに知ってもらいたい、フットサルをメジャースポーツにしたい、その役割を担いたいといった想いもあったように思う。本格的に日本代表のサポーター組織が誕生したことは、フットサルが1人前のスポーツとして育ちつつある証と言えるであろう。
そしてこの悲願達成に向けてポエイラの果たした役割、貢献は大きかった。まず、大きな日の丸の弾幕を用意し、サポーターたちの応援メッセージの書き込みを集め、会場に掲げた。また、揃いのブルーのTシャツを着込み、応援用のスティックバルーンを叩き、気勢をあげた。ただ、サポーターと言っても、当時はまだいわゆるサッカーのサポーター軍団というイメージではなく、団長の山川、サポーターの先駆者であるトヨ、ワカンらに混じって、関東リーグをはじめ地域リーグ関係者、フットサル施設関係者、メディア関係者、選手の家族らが渾然一体となって応援をした。しかし、ワールドカップに出場できれば、フットサル界に明るい未来が開けるという期待を共有した希望に満ちた応援であった。当時の雰囲気を、山川が自身のブログでこう綴っている。
「2004年、マカオで行われるアジア選手権がワールドカップ予選を兼ねることが発表された。僕は選手として2002年のスーパーリーグに(一応)参加していて、代表選手や関係者に友達も多かった。サッカーでずっとサポーターをしてきたこともあり、『フットサル代表の応援を立ち上げるのは俺しかいない!』といつもの勝手な思い込みで行動を始めた。
結局マカオに乗り込んだメンバーはサポーターというよりも関係者の集団だった。クラブの社長からメディア、選手の彼女まで、いろんな立場の人間が一緒にフットサルの未来を夢見ていたイイ時代だったな~。
一緒にいた大人たちもサポーターというものをよくわかっていなかったようで、おもしろい出来事もあった……。応援デビュー戦の中国戦。結果は日本の勝利。その試合後。同行したある大人に呼ばれた。
『おい!太郎!こっち来てくれ!』
見ると、中国サポーターのボスらしき人物をつかまえている。
『熱戦の証に、ボス同士握手をしてくれ』
『え?あ、あぁ、はい』
こんなのサポーターの世界で聞いたことない。ましてや負けた相手に握手されるなんて、中国の彼は屈辱だったろう。しかしその大人の勢いに押され、お互い苦い顔で握手をして記念撮影……。今となっては笑える。あの時代ならではのエピソード。なつかしい」
ということで、お宝写真は、ワールドカップ出場のもう1人の立役者、日本代表応援団を代表して山川太郎の写真にしよう。彼の同じような姿は今も、日本代表、あるいは湘南ベルマーレの試合に行けば見受けられる。
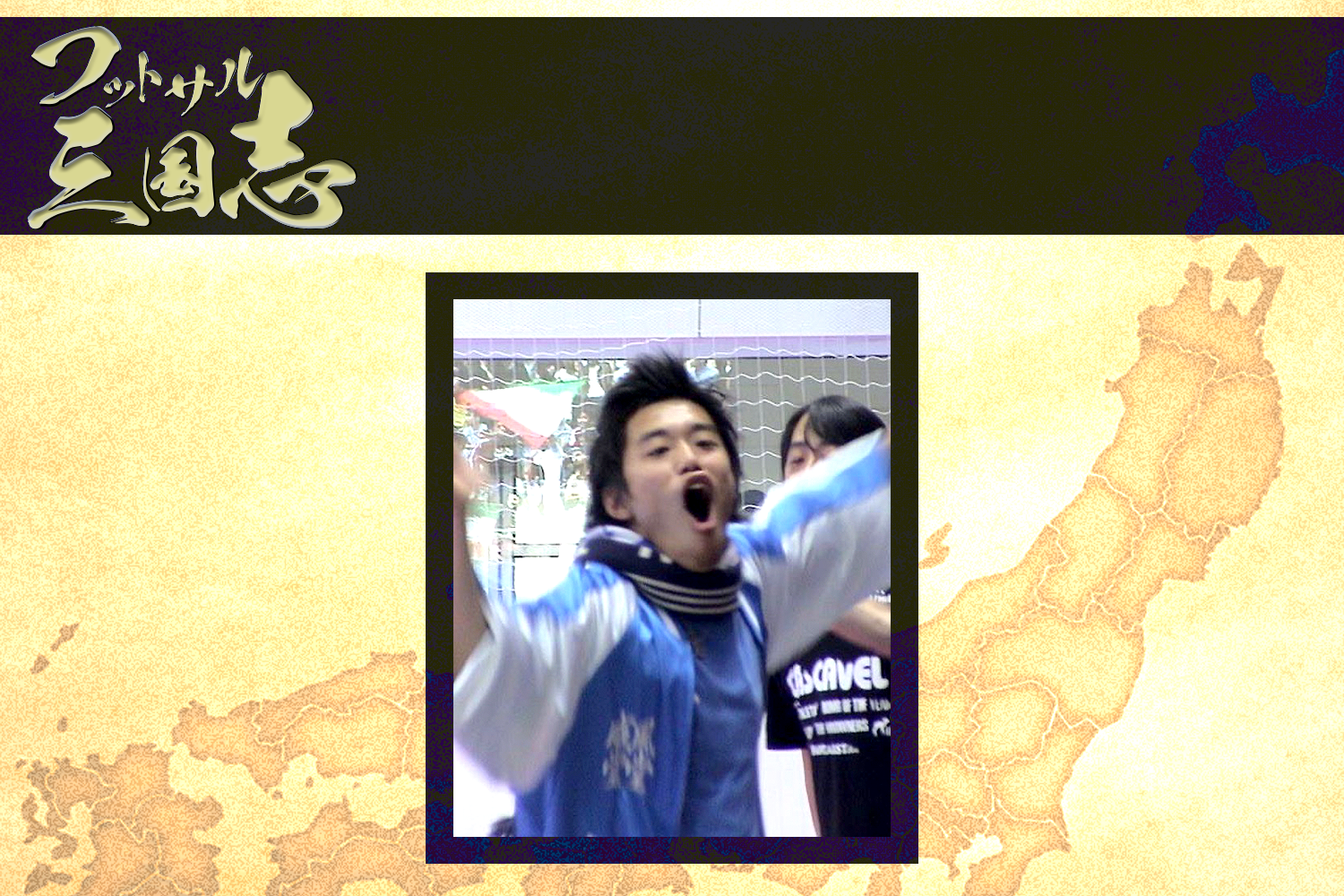
▼ 関連リンク ▼
▼ 関連記事 ▼
-
2026.01.31