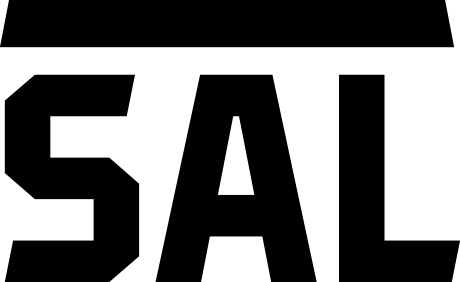更新日時:2022.08.26
高校年代“サッカーvsフットサル”の現在地。恥も外聞も捨てた名古屋U-18はなぜ、敗れ散ったのか。【U-18選手権コラム】

PHOTO BY河合拓
注目された一戦は、大きく期待を裏切る凡戦になりそうだった。そして、名古屋オーシャンズU-18(東海地域代表)は、試合を凡戦で終わらせなければいけなかった。
第9回全日本U-18フットサル選手権大会・準決勝の藤井学園寒川高校(四国代表地域)と名古屋U-18の試合は、「サッカーチームvsフットサルチーム」という、歴代大会でも見どころとされてきた構図の対戦だった。1次ラウンドの成績を見ると、寒川は3試合を3連勝し、29得点・9失点と今大会随一の圧倒的な攻撃力を示していた。
一方の名古屋U-18は、ペスカドーラ町田U-18とシュライカー大阪U-18というFリーグ下部組織2クラブとスコアレスドローを演じ、1勝2分け、6得点・0失点でグループCを2位で通過した。1次ラウンドでの失点ゼロは大会唯一であり、最強の矛と最強の盾のぶつかり合いとも言える一戦だった。
取材・文=河合拓
Fリーグに進路を取る高校年代のサッカー選手
誤解を恐れずに言えば、9回の積み重ねにおいて、サッカーとフットサルは歩み寄りを見せている。2014年に大会が始まった当初のサッカーチームは、フットサルに関する知識をほとんど持っていなかった。今大会も主審に「ゴールクリアランス!」と声をかけられ戸惑うチームはちらほら見られたが、昨今のABEMAのFリーグ無料中継の影響などもあり、フットサルに対する知識は、この9年という時間でサッカーチームにも浸透していった。
具体的な例を挙げると、今大会でFリーグ下部組織の3クラブと同組になった北海道釧路北陽高校(北海道地域第2代表)が分かりやすい。第2回大会で準優勝した時、このチームのキャプテンを務めていたのは、ペスカドーラ町田の伊藤圭汰だった。伊藤はこの大会に出るまで、Fリーグはもちろん、フットサル日本代表の存在も知らなかった。
しかし、今大会に出場した北海道釧路北陽の選手たちは、Fリーグに進路を取り、フットサル日本代表候補にも選出された“伊藤先輩”のことを知っており、高橋健太監督によれば「自分たちにも同じような道が開けるのではないかと、かなり意識していた」状態だった。
フットサル界に流入し始めたポテンシャル
サッカーチームにとって、フットサルの知識不足が課題だったことに対し、フットサルチームの課題は「アスリート不足」だった。もちろん、選手の数はいたものの高校年代で運動能力の高い選手たちは少数派で、フットサルチームはセットプレーやサインプレー、守備のセオリーなど、専門性を武器に対抗していた。だが、現在はアスリート能力の高い若い選手も、フットサルチームに加入する状況ができつつある。
こちらの例としてわかりやすいのは、名古屋U-18に所属するU-19フットサル日本代表候補のGK物部呂敏だ。物部は、中学生年代までは名古屋グランパスU-15に所属していた。しかし、サッカーのGKとしては、身長が足りなかったこともあり、高校年代からはフットサルをプレーすることを選択し、国内唯一のプロフットサルクラブである名古屋オーシャンズの下部組織の門をたたいた。もちろん、まだまだ例は少ないが、こうしたJリーグの下部組織に入っていてもおかしくないアスリート能力の持ち主が、徐々にフットサルチームでも見られるようになっている。
トップチームが「王者」であるがゆえの重圧
こうした状況のなか、第6回大会では町田U-18がフットサルチームとして、初の全国大会優勝を成し遂げていた。今大会でもフットサルチームの躍進が見られるかは、注目ポイントの一つだった。
Fリーグが誕生する直前からこれまで、日本のフットサルを名古屋オーシャンズが引っ張ってきたのは、誰もが認める事実だろう。しかし、U-18フットサル選手権大会における名古屋U-18は、第1回大会で決勝に進出して以降、準決勝に勝ち残ることもできていない。日本中から最高の選手を集める名古屋のトップチームに対し、名古屋U-18は、名古屋近郊に住む高校生たちで構成されている。そのため、東海大会を勝ち上がれない年も、少なくない状況だ。
とはいえ、周囲はそのようには見てくれない。どうしても「絶対王者の下部組織なのに、今年も勝てなかったの?」と見られてしまう。その意味では、トップチームが絶対的に強いがゆえに、他クラブ以上に、大きなプレッシャーがのしかかっているチームなのだ。そこで彼らは、一つの覚悟を示した。
準々決勝、名古屋U-18は“勝つ戦い”を選んだ。1次ラウンドでサッカーチームを相手に打ち合う試合を演じてゴールを量産した寒川に対して、FP4人全員がハーフウェーラインまで引き、スペースと時間を与えなかった。
ここまでフットサルの専門チームと対戦した経験がなかった寒川が、名古屋U-18の守備ブロックの周りでボールを回し、攻め手を見つけられないまま時間がどんどん流れていく。名古屋U-18は、ボールを奪ってからもむやみに速攻を仕掛けることはなく、時に物部も攻め上がって、数的優位をつくってボールを回してシュートチャンスを生み出していた。そして26分までに藤田航輝が2点を挙げ、リードする展開に持ち込んでいた。
簡潔に言えば、攻撃でも守備でも、名古屋U-18は完全にリスクを排除した戦い方を見せて、確実にベスト4進出を決めにいく戦いぶりだった。勝負における理には適っていたが、見ている第三者からすれば、極めて退屈な試合でもあった。ただ同時に、フットサルチームがサッカーチームに対して、確実に勝つには有効な戦い方にも見えていた。
周到だった“サッカーチーム”藤井学園寒川高校
30分までこの試合を見ていた人たちは、名古屋U-18の勝利を確信していただろう。実際、第2ピリオド途中に会場を離れた知り合いのFリーグクラブ関係者から、「あの後、何が起こったの?」という連絡をもらった。
今大会の1次ラウンドは15分ハーフで行われたが、決勝ラウンドからは20分ハーフで行われた。本来ならば、日常的に20分プレーイングタイムで練習試合などを行っているフットサルチームが優位になるはずだ。だが、この試合はそうならなかった。
物部が「1次ラウンドだったら、もう2-0のまま試合が終わっていました。その感覚のズレがあった」と振り返った一方で、プレーイングタイムの20分ハーフを経験したことがなかった寒川は、最初からこのラスト10分間にすべてを賭ける腹づもりだったという。寒川がスイッチを入れたのは、32分に取ったタイムアウトの時だった。
寒川の岡田勝監督は試合後、このように振り返った。
「準々決勝を前に『絶対に失点するだろう』と話していました。また『相手は失点ゼロで勝ち上がってきたチームだから、我慢比べのゲームになるぞ』と確認していたんです。今日から20分プレーイングタイムになって、オーシャンズさんは上手にメンバーを入れ替えてやっていますが、私たちは限られた人数で戦っているので、時間をうまく使いながら、前半途中まで相手のウィークポイントを探り、最後にスキを突く形を考えていました。戦略としては『残り10分から勝負しよう』と。そこまでは、我慢比べでしたね」
名古屋U-18の守備ブロックの前で、単調なボール回しに終始していたのは、あえて仕掛けずに、最後の10分に向けて体力を温存する狙いがあったのだ。寒川で、実際に細かく指示を出していたのは、ベンチの永田凱聖だった。本来は中心選手の一人だが、大会直前にヒザの靭帯を負傷。ベンチ入りしたもののプレーはせずに、戦況を見て、チームメートに指示を送っていた。寒川の強みは、なんといっても1次ラウンドの3試合で10得点を挙げた10番・三宅悠斗と、9得点を挙げた11番・牧敬斗のコンビである。永田は、前後半のタイムアウトで伝えた指示について、こう明かした。
「うちのピヴォ(三宅)が厳しくマークされていたのは、前半に入ってすぐに分かりました。そのピヴォをサイドに開かせることで、中央のスペースが空きます。そこに11番がカットインしていこうという話をしたのが、前半のタイムアウトでした。後半の時は、サイドに開く10番の動きに相手がついてこなくなり、11番のところでつぶして、取り切る形になってきていました。そこで相手のフィクソがボールを奪いに行ったら、10番が寄ったフィクソの背中を回って、もう1回ゴール前に顔を出して、ピヴォ当てを受けられるようにしようと、指示を出していました」
第2ピリオドでタイムアウトを取った寒川は、共通の狙いを持って名古屋のゴールを目指すことができていた。36分、高い位置でボールを奪った牧が仕掛け、中に入れたボールをピヴォの三宅が決めて1点を返す。そして、試合終了間際、残り56秒には、まさに永田の指示通りの動きから、ゴール正面に入った三宅が同点ゴールを挙げた。
永田は、「高校サッカーをしているから、タフな選手が多い。そこは自信がありました。県大会からも、こういう展開の試合が多かったので、変な自信がありました」と、最後の10分間に爆発できる余力があると信じていたと言う。
また、三宅は1点目を挙げた後、38分に名古屋U-18が取ったタイムアウトの影響に触れた。「あれがいいタイミングで、ありがたかったです。ピヴォなので、前から追いかけていて、しんどい時間帯でした。あそこで休めたのは大きかったです」と、FPをわずか5人で回していたチームの疲労軽減につながったと明かした。
追い込まれて崩れた“フットサルチーム”名古屋U-18
名古屋U-18の赤窄孝監督は、残り10分に向けて「プラン通りにやることが、すごく難しかった」と、悔しがる。名古屋U-18は30分、U-19日本代表のクロアチア遠征にも参加していた伊集龍二が、三宅との接触で負傷。最後尾でゲームを組み立てるフィクソがいなくなり、ボールを持った際に急いでピヴォに当てる場面が増えていた。
「試合中にも負傷者が出て、普段のセット起用が難しくなりました。チームの方針を変えずに、時間をうまく使いながらやることは考えていました。そのなかで、ビデオミーティングでも『リスクを背負わずにやろう』と話していたのですが、うまくいかなかったですね。(タイムアウトは)戦術的なところよりも、メンタル的なところで必要だと感じました」(赤窄監督)
チームは、確実に追い込まれていた。さらに物部は、メンタル面でチームが崩れた要因として、伊集が負傷でいなくなったことに加え、1次ラウンドから無失点だったことを挙げた。
「2-0の時は、自分たちでボールを持とうとして、できていました。でも、2-1になってからは『シンプルにやろう』と話したけれど、うまくシフトチェンジができずに、プレーを切らないといけなくなっていました。1次ラウンドで失点していないなかで初失点を喫して……。事前にこうなる可能性があることは分かっていたから『失点しても仕方がないから、次だよ』と話していたし、失点直後もみんなを集めて話したんですけど、どうしても流れを変えられずに崩れちゃいました」
このままPK戦に入った場合、名古屋U-18の優位だと思われた。フットサルのPKに慣れていることに加え、ゴールを守る物部の存在があったからだ。しかし、残り56秒で追いつかれたことによる焦りは、シンプルなプレーにズレを生じさせ、選手たちの冷静な判断力を失わせてしまった。
語り継ぎたくなる高校年代のフットサル名勝負
残り4秒、味方からのバックパスがズレて、物部に入る。ボールをコントロールして、大きく蹴ろうとした物部だったが、これを狙っている男がいた。ここまで2ゴールを挙げていた、三宅だ。
「映像を分析した時に、名古屋はGKがボールを持つことが多かったのですが、ちょっともたつく印象を受けました。すごく実力のある選手ですが、スッといけば、追いつくかなと。自分は、瞬発力に特徴があるので狙っていました」
物部が持ち直したボールを奪った三宅は、そのまま無人のゴールに決勝点となるシュートを流し込み、40分で決着をつけた。
試合後、名古屋のチームスタッフの一人は「恥を捨てて、あのやり方で戦ったのに、この結果は……」と、8年ぶりのベスト4進出を逃しただけではない敗戦に悔しさを滲ませ、物部も「次につなげるしかないのですが、こうなっちゃうと『サッカーの落ちこぼれがフットサルをやっている』と思われてしまう。木暮賢一郎監督も『俺は絶対に言われたくないから、必死にやってきた』と言っていましたが、そういう結果になってしまった」と、肩を落とした。
様々な要素が複雑に絡み合って決した勝敗には、様々な解釈がなされるだろう。まだ10年にも満たない歴史の浅い大会に、また一つ語り継ぎたくなるような名勝負が刻まれた。