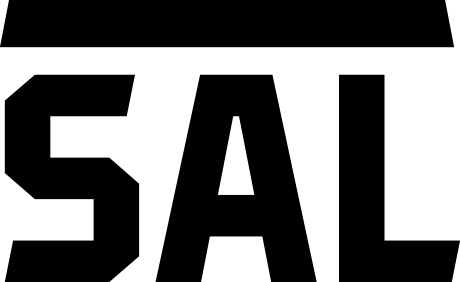更新日時:2022.10.20
元Fリーグ&日本代表アジア覇者・佐藤亮“監督”が見た景色。大阪成蹊大を初優勝に導いた化学反応とは?【全日本大学コラム】

PHOTO BY河合拓
2022年8月、第18回全日本大学フットサル大会で初優勝に輝いた大阪成蹊大学。チームを頂点へと導いたのは、Fリーグでも活躍した元日本代表・佐藤亮監督だ。
シュライカー大阪時代、2016-2017シーズンに名古屋オーシャンズ以外で初めてFリーグを制覇したチームでキャプテンマークを巻いた。2014年のアジア選手権(現アジアカップ)では日本代表としてアジア制覇も経験した。現役時代からフットサル界の第一線を走ってきた佐藤監督は、指導者として大きな成果を挙げた。
大阪成蹊大で初めて「監督」に就いた彼は、選手たちにどのようなアプローチをしたのか。選手のモチベート、戦術的アプローチ、監督としてのチャレンジ、数奇な巡り合わせ、大会中止に泣いた卒業生の思い……さまざまな要素が複雑に絡み合い、辿り着いた栄冠。佐藤監督の功績は、後に続く指導者にとっても、勇気を与えるものかもしれない。
文・写真=河合拓
佐藤亮監督と選手の信頼関係
「落とすなよ! 絶対に落とすなよ!」
表彰式後に記念撮影が行われ、ひとしきりの歓喜の後、監督の胴上げが始まる直前に選手たちから冒頭の声が挙がった。
大阪や日本代表で活躍した現役時代とほとんど変わらない、細身の指揮官は、「おい!」と反応し、胴上げを拒否しようとする。だが、すぐに選手たちに取り囲まれてしまい、高く宙を三度舞って、最後は“しっかりと”床に落とされた。落下する直前には、もちろん数人の選手が衝撃を和らげようとしたが、それによってバランスが崩れ、結果として軽く肩を打った佐藤亮監督は、肩をさすりながらも笑顔だった。
監督と選手たちの関係が極めて良好であることは、この場面を見てもうかがえた。
これまで、大学選手権において大阪成蹊大は2016年大会、2017年大会で準優勝、2018年大会で3位と上位に入賞していたが、優勝には手が届かなかった。今回、初めて大学フットサル界の頂点に立てた要因として、佐藤監督を抜きに語ることはできない。
優勝を決めた後、選手たちも口々に、優勝の要因に「佐藤監督の存在」を挙げている。キャプテンの中村魁は、「頼りがいがあるというか。選手としてもすごい人でしたし、尊敬できるところもすごく大きいです。普段は優しいですが、厳しい時は、厳しいです」と、その指導スタイルを明かした。
「立ち向かわせる」モチベーション
大会初戦の相手は、初出場の東京大学フットサル部さんぱち先生。全国で最難関である関東予選を勝ち上がってきた相手に、鮮やかなセットプレーから先制点を許してしまったが、その後に5点を挙げて5-1の逆転勝利を収めている。その要因の一つには、「今大会で最注目のピヴォ」との前評判のあった城後大樹を抑え込めたことがあった。
佐藤監督はあえて城後にボールを入れさせて、フィクソの選手たちに勝負させた。
「そこの勝負かなと思っていました。20番の城後くん、21番の峰岸(剛基)くん。彼ら2人が仕事をしたら相手のリズムだし、そこをうちの橋本(澪良)、森本(碧)、今日でいえば吉迫(武隆)が止めれば、自分たちのリズムになるとは、試合前から言っていました。彼らもそういうモチベーションをもってやってくれたのかなと思います」
ピヴォの選手たちへのパスの供給源を断つこともできたが、そうしなかった理由については「迷ったんです。最初からハーフまで引くことも考えたのですが、この年代特有の“立ち向かわせることでのモチベーション”に期待して、そういう戦術にしました。期待に応えてくれたというか、自分の思った通りにプレーしてくれたので、全選手、本当にいいパフォーマンスをしてくれたと思います」と、説明している。
ほかにも、1-1の時には、GKの片岡浩太が攻め上がって豪快なシュートを決めた。「プレス回避の時とか、攻め上がることはよくあるんです。あそこまでいいシュートは見たことなかったのですが、関西リーグや学生リーグでも点を取っていて、そういうプロフィールを持っている選手です。試合の流れを変えた1点かなと思います」と、佐藤監督は選手の手柄であることを強調した。
だが、しっかりとGKを加えた攻撃を教えられる指導者は、まだ決して多くない。
木暮賢一郎監督から学んだこと
決勝を含めても、試合の状況や展開に応じた微修正ができる点も大きい。少しオーバーな表現をすれば、トップレベルのフットサルでは選手たちが駒のように動き、監督の描く戦略プランを遂行するようになっている。日本代表の木暮賢一郎監督が、先日のアジアカップを制した戦い方が、まさにそれだ。目の前で起きている現象に対して指導者がどのような解決策を示せるかは、今後の大学フットサル界で勝っていくうえで、これまで以上に求められていくはずであり、そうならなければならない。
佐藤監督や多摩大学の福角有紘監督、また、今大会初出場の東京国際大学サッカー部を率いたバサジィ大分初代監督・境大輔氏など、日本代表経験者やFリーグの監督経験者が、少しずつ大学フットサル界に流れ込み、レベルアップを促進していることは間違いない。
現役時代にミゲル・ロドリゴ元日本代表監督や、現日本女子代表監督・須賀雄大氏の指導を受けた佐藤監督だが、指導者として大きな刺激を受けたのは、極めて最近のことだという。今年6月に行われたU-19日本代表のクロアチア遠征にフィジカルコーチとして帯同し、木暮監督や高橋健介コーチ、内山慶太郎GKコーチと仕事を共にし、試合に向けた分析を含めたチームビルディングを体験した。
「今大会は、その時の経験を駆使して戦いました。指導者として僕は、まだまだ。現役時代に多くの監督の下でプレーしていましたが、彼らがどんな準備をしていたかまでは分かりません。大阪で比嘉リカルド監督(現・立川アスレティックFC監督)の下でプレーした時の経験も生きていますが、木暮監督から受けた影響も大きいです」と、大阪でFリーグ制覇を成し遂げ、現在はフル代表とU-19日本代表の監督を兼務する指揮官から学んだモノの大きさを語っている。
また、準備段階で佐藤監督の人脈が生きた。「自分が携わるようになって、一番の変化」と言うように、古巣の大阪をはじめ、Fリーグのクラブとの練習試合も積極的に行うようになった。
「学生リーグのレベルが高いかというと、決してそうではありません。現状で満足しないように刺激を与えていて、大会直前にはデウソン神戸、アグレミーナ浜松、名古屋オーシャンズサテライトと練習試合をしました。それによって、選手もトップレベルで求められる感覚が分かりますし、練習の強度も上がります。レベルの高い相手と接点を持つことでモチベーションは上がりますし、レベルアップのきっかけにもなる。いい選手だと認められたら、引っ張られるかもしれません」
「紅白戦が一番レベル高い」伝統
佐藤監督の存在が大阪成蹊大の初優勝に大きな後押しとなったのは間違いない。だが、自分自身はあくまで“ラストピース”であると強調する。佐藤監督が指導者としての能力を発揮できる土台が、前任者によって作られていたという。2003年に創部された大阪成蹊大フットサル部では、2004年から佐藤監督が就任する2020年まで、柴沼真氏がチームを率いていた。
「大前提として、前任の柴沼先生が創部当初のフットサル部を率いて、大学生が競技フットサルに取り組める土壌や文化を築いてくださっていたことがあります。今では体育館にもフットサルコートが描かれていますが、柴沼先生が就任した直後は、フットサル部に人が全然いませんでした。練習をしようとしても、人が集まらない。競技志向に踏み切れないところをハード面から整備し、さらに大阪成蹊大の活動にとどまらず、関西学生リーグを大きくしていきました。フットサルに取り組む環境づくりを行うとともに、フットサル部にスポーツ推薦の選手が加入できるようにして、自ら高校の大会なども視察して、有力な選手を集めてくれました。そういう土台があったうえで、自分はパッと任せてもらった感じなんです」
詳しく聞けば、あまりにも運命的な邂逅だった。佐藤監督が大阪成蹊大の指導に関わり始めたのは、2014年4月のこと。当時、大阪成蹊大のコーチを務めていた永井義文(現・大阪監督)がイタリアのクラブへ移籍することになり、その後任として、新コーチの役目が回ってきた。約2年、大阪成蹊大コーチを務めたが、帰国した永井氏が大阪成蹊大のコーチに復帰。その後、佐藤監督は大阪で比嘉監督の下、トップチームのコーチを務めた。2020年から永井が大阪サテライトの監督となり、トップチームの監督に就任。同じタイミングで大阪成蹊大の柴沼監督が、家族が生活をしている関東に戻ることになり、大阪成蹊大の監督のポストが佐藤氏に巡ってきたのだ。
監督就任後、選手にまず要求したのが練習の強度だった。それまでは負傷しないようにと、ぶつかり合いが起こらないような状況だったが、公式戦さながらの激しさを求めた。現在は紅白戦でもバチバチと激しく削り合う姿が日常的であり、「チーム内競争は、みんな嫌になるくらい熾烈です。紅白戦も強度が高くて、公式戦に出場した後にも『紅白戦が一番レベル高かった』という声が挙がっていました。実際、紅白戦ではできないようなプレーが大会では出ていましたし、フィジカルを含めて、うちの紅白戦はレベルが高いと思います。僕が現役の時、アジア選手権(現アジアカップ)を制した日本代表も、Fリーグを制した時の大阪も、紅白戦はバチバチで、チーム内の競争は激しかった。そういう伝統が出来上がりつつある」と、手応えを感じている。
先輩たちの“悔しさ”を胸に頂点へ
『伝統』という言葉が出たのには、理由がある。佐藤監督が感じていた手応えは、今年に限ったものではなかったからだ。だからこそ昨年、一昨年の大会中止には、今もやり切れない思いが残る。
「コロナ禍の影響もあって近年は試合数が減っていますが、大阪成蹊大は、1年フルで戦うと年間50試合くらいはあります。関西大学リーグだけではなく、社会人の関西リーグにも出場していますし、全日本選手権、全日本大学選手権、大学の地域チャンピオンズリーグもある。土曜の夜に社会人のリーグ戦を戦い、翌日の朝に学生リーグというスケジュールのこともあって、多くの公式戦を戦えているんです。大学の理解があり、フットサルをできる土壌があり、選手の質も担保されていた。昨年、一昨年も大学選手権の出場資格を得ていましたし、十分に力のある選手たちがいました。大会が開催されていれば、彼らが初優勝を成し遂げていても全く不思議ではありませんでした」
コロナ禍の昨年、一昨年、大学選手権は中止を余儀なくされた。佐藤監督も選手たちも、日本サッカー協会が発表したリリースで中止を知らされたという。緊急のオンラインミーティングを開いたが、「みんなここを目指して大学生活を送っていたから、誰も何もしゃべれない状態でした」。
3年ぶりに開催された今大会、開幕前に佐藤監督は「インカレ(大学選手権)に出場できなかった先輩たちの分も、楽しんで戦おう」と、選手たちに声をかけていた。そして、全国大会を奪われた昨年と一昨年の4年生たちに向けて、卒業生のLINEグループを通じて、「もしよかったら、初の全国制覇を目指す後輩たちにメッセージを送ってほしい」と呼びかけた。
そして昨年の主将・久保田翼、エスポラーダ北海道に加入した山本航平らが、反応した。その前後で起きたやりとり、おそらく今後も消化できないであろう彼らの思いを佐藤監督は明かした。
「涙なしに見られないメッセージでした。選手たちもそれを見て、『先輩たちの分も、自分たちがやろう』という思いを強くしてくれた。本当に失われたものは、計り知れないと思う。甲子園が中止になったのと、意味合いとしては同じです。なかには高校生の時にインカレを見て、この大学に来たいと言っていたのに、最後の最後に中止になってしまった選手もいました。優勝が決まってから、久保田と話をしましたが、『うれしさがある反面、悔しさも大きい。後輩たちの頑張りはうれしかったが、見れば見るほど、自分たちも戦いたかった』と言っていました」
写真右から2番目が昨年の主将・久保田翼。両端が昨年のマネジャー(本人提供)
前人未到の4連覇へのチャレンジ
優勝の要因を一つに絞ることは不可能だ。様々な事象が複雑に絡み合い、チームが化学反応を起こす。そこにさらに、対戦相手という自分たちにはどうしようもできない要素も絡んでくる。また、ちょっとしたジャッジなど、“運”も大きく結果を左右する。ただ間違いなく、大阪成蹊大は可能な限りの準備をして大会に臨み、大会中も成長し、初の全国制覇を成し遂げた。
大会を終えて、「初めて監督として、何かをやり遂げた感覚がある」と話した佐藤監督は、すでに来年夏の連覇へと気持ちを切り替えている。
「現役時代を含めて自分自身、連覇したことがありません。大阪はオーシャンカップを連覇していますが、僕の加入前でした。一度、ガッとパワーをかけて、優勝することはできても、それを続けていくことは未知数であり、自分自身にとってもチャレンジ。今の1年生が入ってきた時に、『前人未踏の4連覇を成し遂げて、歴史を変えよう』という話をしました。責任をもって、やり遂げたい」
これまでの大学フットサル選手権の歴史で、神戸大と順天堂大が3連覇を成し遂げているが、4連覇したチームは一つもない。佐藤監督率いる大阪成蹊大は2022年大会の初優勝を足掛かりに、日本の大学フットサル界をけん引する存在となっていけるだろうか。